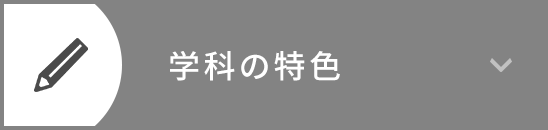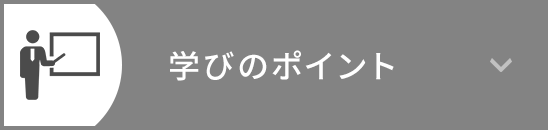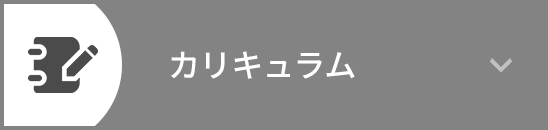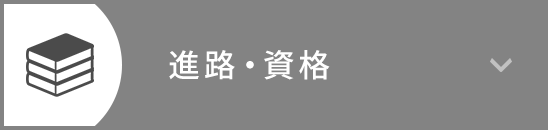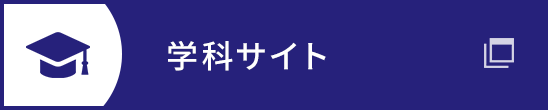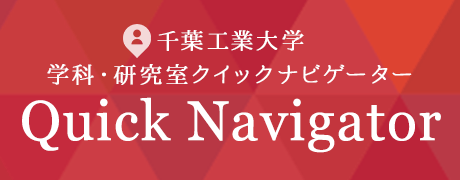都市環境工学科

「快適さ」「便利さ」「安全」など広い視野をもった社会インフラやまちづくりの専門家を育成します。
| POINT 1 |
| インフラ構築、都市計画・ 環境保全を体系的に学びます |
| POINT 2 |
| 実践的な授業でプレゼンテーション能力、 協働力を養います |
| POINT 3 |
| 各種資格が取得できる カリキュラムを用意しています |
学科の特色
まちづくりは総合的な学問。広範な知識と課題解決力を身につけます。
便利であること、快適であることに加え、災害に強い、環境への負荷が少ないなど、まちづくりには実にさまざまな視点が求められます。本学科は建設材料や構造力学など社会インフラそのものに関わる授業のほか、環境アセスメントや交通、衛生、環境音響、景観工学に至るまで幅広い知識を習得。さらには演習を通して、実践的なまちづくりや景観づくりの手法、プロジェクトを遂行する力なども身につけていきます。カリキュラムは工業、建築系の資格取得にも対応。さらにまちづくりに不可欠な住民の理解を得る能力を身につけるため、演習を通してコミュニケーション力やプレゼンテーション力も養っていきます。
ディプロマ・ポリシー
都市環境工学科は,以下のような知識・技術・能力等を身につけ,所定の単位を修得した学生に学位を授与する。
(1) 都市環境工学に関わる自然科学,社会科学等に立脚した基礎知識,基礎的技術を修得している。【知識・理解(専門基礎・専門基幹)】
(2) 都市環境工学を構成する各分野の専門的知識・技術を修得し,それらを現実の都市環境工学分野の問題と結びつけて考えることができる。【総合的学習(専門展開)】
(3) 長期的視点をもって,環境や社会と調和する社会インフラ,都市・地域の計画・設計ができ,その成果を他者に分かりやすく伝えることができる。【創造的思考(専門展開)】
都市環境工学科は,以下のような知識・技術・能力等を身につけ,所定の単位を修得した学生に学位を授与する。
(1) 都市環境工学に関わる自然科学,社会科学等に立脚した基礎知識,基礎的技術を修得している。【知識・理解(専門基礎・専門基幹)】
(2) 都市環境工学を構成する各分野の専門的知識・技術を修得し,それらを現実の都市環境工学分野の問題と結びつけて考えることができる。【総合的学習(専門展開)】
(3) 長期的視点をもって,環境や社会と調和する社会インフラ,都市・地域の計画・設計ができ,その成果を他者に分かりやすく伝えることができる。【創造的思考(専門展開)】
カリキュラム・ポリシー
都市環境工学科のディプロマ・ポリシーで定めた各能力を修得させるため,以下に示す教育課程編成における3項目の具体的な方針を定める。
(1) 都市環境工学の基礎となる数学,物理学,化学等の自然科学,製図基礎を修得する科目,都市環境工学全体を概観する科目として,専門基礎科目を配置する。また,都市環境工学を構成する構造,材料,地盤,水理,環境,計画の6分野における基礎知識を修得するための専門基幹科目を配置する。
(2) 構造,材料,地盤,水理,環境,計画の各分野における専門的知識を深め,高度な専門的技術を修得するための専門展開科目を配置する。なお,各科目の実施・運営にあたっては,修得した専門的知識・技術を現実の都市環境工学分野の問題と結びつけて考える機会を提供する。
(3) 長期的視点で環境や社会と調和する社会インフラ,都市・地域を計画・設計する能力,その成果を他者に分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力を修得するための都市環境工学全般に関わる実験科目・演習科目を配置する。また,4年次においては,知識と知識を連結し,現実の都市環境問題を解決できる技術者としての総合力を修得するためのゼミナール,卒業研究を配置する。
都市環境工学科のディプロマ・ポリシーで定めた各能力を修得させるため,以下に示す教育課程編成における3項目の具体的な方針を定める。
(1) 都市環境工学の基礎となる数学,物理学,化学等の自然科学,製図基礎を修得する科目,都市環境工学全体を概観する科目として,専門基礎科目を配置する。また,都市環境工学を構成する構造,材料,地盤,水理,環境,計画の6分野における基礎知識を修得するための専門基幹科目を配置する。
(2) 構造,材料,地盤,水理,環境,計画の各分野における専門的知識を深め,高度な専門的技術を修得するための専門展開科目を配置する。なお,各科目の実施・運営にあたっては,修得した専門的知識・技術を現実の都市環境工学分野の問題と結びつけて考える機会を提供する。
(3) 長期的視点で環境や社会と調和する社会インフラ,都市・地域を計画・設計する能力,その成果を他者に分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力を修得するための都市環境工学全般に関わる実験科目・演習科目を配置する。また,4年次においては,知識と知識を連結し,現実の都市環境問題を解決できる技術者としての総合力を修得するためのゼミナール,卒業研究を配置する。
1年次
製図や模型製造など設計工程に不可欠な基礎を学びます
数学、物理学、化学などの基礎を学び、構造力学や建設材料工学を通して建造物の構造を理解します。また、計画系や環境系の知識も基礎演習の中でしっかりと身につけます。
数学、物理学、化学などの基礎を学び、構造力学や建設材料工学を通して建造物の構造を理解します。また、計画系や環境系の知識も基礎演習の中でしっかりと身につけます。
2年次
都市環境工学に直結する専門科目を学修します
道路や橋などの建造物の設計に不可欠な構造力学、水理学、土質力学を本格的に学びます。また、総合的なプランニングに関わる都市計画や環境アセスメントなども学修します。
道路や橋などの建造物の設計に不可欠な構造力学、水理学、土質力学を本格的に学びます。また、総合的なプランニングに関わる都市計画や環境アセスメントなども学修します。
3年次
自治体と連携した実習や実験で実践力を身につけます
「都市環境工学演習」では半年かけて実際のまちをどう活性化するか考え、自治体の職員に向けてプレゼンテーションとディスカッションを行います。
「都市環境工学演習」では半年かけて実際のまちをどう活性化するか考え、自治体の職員に向けてプレゼンテーションとディスカッションを行います。
4年次
卒業研究を通して都市づくりに必要な総合力を養います
研究室に所属して卒業研究に取り組みます。都市環境の課題を発見し、住民や行政などの要望を踏まえながら、多角的に分析し、改善計画や新たな手法を考察する力を養います。
研究室に所属して卒業研究に取り組みます。都市環境の課題を発見し、住民や行政などの要望を踏まえながら、多角的に分析し、改善計画や新たな手法を考察する力を養います。
- 地方公務員(県庁、市役所など)
- 国家公務員(国土交通省、環境省など)
- 総合建設会社の設計者・施工管理技術者
- 都市計画・環境・建設コンサルタント
- 景観デザイナー
- 測量会社
- 鉄道・高速道路・エネルギー会社(企画・設計・施工管理)
- 不動産・住宅会社(企画・設計・施工管理)
- 専門性を備えた教員 他


取得できる資格
- 高等学校教諭一種免許状【工業】
- 測量士★
- 測量士補
- 二級建築士※
- 木造建築士※
- 建設機械施工管理技士(1級・2級)※★
- 電気工事施工管理技士(1級・2級)※★
- 電気通信工事施工管理技士(1級・2級)※★
- 管工事施工管理技士(1級・2級)※★
- 建築施工管理技士(1級・2級)※★
- 土木施工管理技士(1級・2級)※★
- 造園施工管理技士(1級・2級)※★
- 技術士補